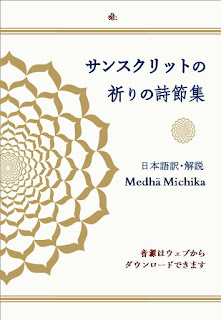伸ばす母音に注意しましょう。
ラーマという名の王子の人生を描いた物語(アヤナ)
ですから、
ラーマ + アヤナ = ラーマーヤナ
となります。
長短を無視して、日本では「ラマヤナ」とか、
ラテン系だと「ラマヤ~ナ」など、いろいろ間違われているようですが、
正確には「ラーマーヤナ(रामायणम् [rāmāyaṇam])」です。
最初の2つの音節が長く、続く2つの音節は短く発音します。
ちなみに、最後の「ナ」 は舌を内側に反らして発音します。
詳しくは、下の「文法的な説明」 を参照してください。
サンスクリット語には、母音の長短の違いで
意味が全く変わってしまう単語が多々あります。
そしてなにより、口伝により継承されて来たサンスクリット語においては、
発音の正確さはとても重要ですから、
ひとつひとつの音を、マインドフルに発音しましょうね。
日本でよく見かけられる、母音の長短の間違いが起きている言葉は、
ヴェーダーンタ、サードゥ、プージャー、プラーナーヤーマ、等々でしょうか。
特に、短い i と u で終わる単語の最後が伸ばされているのと、
長い ā で終わる単語の最後が伸ばされていないのが気になります。
あと、日本語の小さい「ッ」のように、詰まるべき音が、
日本人の場合、詰まっていない、というのも気になります。
サティヤ、ニドラー、等々、このタイプはたくさん見かけます。
文字だけ追いかけていないで、きちんと耳から学んでくださいね。
ちなみに、1拍の長さの母音は、ह्रस्व [hrasva]と呼ばれ、
2拍の長さの母音は、दीर्घ [dīrgha]と呼ばれます。
発音する時は、長さの区別をしっかり意識して、
正しい発音を身につける努力をしてください。
「ラーマ」とは、今でも存在するインド北部の都市アヨーディヤーの、
ダシャラタ王の息子である、王子の名前です。
「ラーマ(रामः [rāmaḥ])」の語源に関しては、
それだけでひとつの記事になるので、後日書きますね。
ヴィシュヌ神が、人間にダルマとは何かを体現して見せるために、
「ラーマ」という人間の姿をしてこの世に表れ、
その人生を描いた物語の文献「アヤナ」が、
「ラーマーヤナ」です。
”रामस्य चरितान्वितम् अयनं शास्त्रम् [rāmasya caritānvitam ayanaṃ śāstram]”
ラーマの行動に沿った文献
शब्दकल्पद्रुमःという梵梵辞典より
「アヤナ(अयनम् [ayanam])」は、
「行く」という意味の動詞の原形「अय् [ay]」を語源としています。
サンスクリット語の「行く」という言葉には、
様々な意味合いがあります。
単に、地点AからBへの移動、という意味もありますし、
その人の人格の表れである「行動」や、
そのような行動の連続である「人生・生き方」という意味、
そして「達成・成功」「ゴール」という意味もあります。
これらの意味が「アヤナ」という言葉に含まれます。
さらに、それらに沿って著わした「文献」という意味もあります。
「ラーマーヤナ」という言葉は、サマーサ(複合語)というタイプの派生語です。
ヴィッグラハ・ヴァーキャ(派生語を説明する文章)は、
रामस्य अयनं रामायणम् ।
rāmasya ayanaṃ rāmāyaṇam |
となりますね。
サンスクリット語を学び始めたら、早い段階でサマーサを学ぶと良いですよ。
あと、अयन の न् が、ण् に変化するのは、राम の र् が原因です。
しかし、このルール(8.4.1, 8.4.2)が適用されるのは、
ひとつの単語内においてのみです。
サマーサの中の、前の単語(पूर्वपद [pūrvapada])にある原因が、
後ろの単語(उत्तरपद [uttarapada])にある न् を変化させることは出来ません。
しかし、8.4.3 पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः। というスートラにより、
固有名詞に限っては、サマーサの前後の単語にまたがった ण् への変化が認められています。
ダルマの元型、ダルマとは何か、のアーキタイプ、
それがラーマです。
ダルマの体現である主人公ラーマが、
難しい状況をどのように乗り越えていくのかを、
物語から学び、ダルマを学びます。
この宇宙において、理性を与えられている生命体を人間と呼び、
その理性を正しく使って、その場その時の状況を判断し、
適切な行動を選びとり、実行できる人を、
ダルマに沿った人、つまり精神的に成長した人と呼びます。
思考ストップして、自分の頭を使わずに、
ただただ盲目的に宗教や国家の教義に従うのではないのです。
この宇宙の創造主は、契約書にサインすることを人間に課しているのではなく、
人間に理性を与えることにより、自分で理性的に考えることを課しているのです。
しかし、日々の生活の中で展開される状況は、
何が適切なのか、簡単に判断できないことが少なくありません。
ゆえに、ラーマーヤナやマハーバーラタなどの物語から学ぶのです。
これらの物語は、登場人物たちの判断の失敗から成り立っています。
ダルマが最重要視されるバックグラウンドにおいて、
様々な過去を持つキャラクターが、様々な難しい状況の中で、
それぞれに判断を下し、物語が進みます。
私たちに考えさせるための内容であり、
盲目的に何でも賛美して追従するための内容ではありません。
ヴェーダーンタはもちろんですが、このような歴史物語も、
ダルマとモークシャを知る先生から学ぶ必要があります。
ラーマーヤナは、ヴァールミーキという名の著者によって、
サンスクリット語の韻文律に沿って描かれた歴史物語です。
それをもとに、インド各地の言語でご当地ヴァージョンのラーマーヤナが生まれました。
北インドでは、トゥラシーダーサのラーマーヤナが有名です。
ラーマーヤナという文献は、イティハーサという種類に分類されます。
イティ・ハ・アーサで、「ということでしたとさ」のような意味になることから、
歴史物語は、イティハーサという名前で呼ばれます。
https://valmikiramayan.net/
ソースとしては、こちらのサイトが充実していますが、
インドの文献は自分で勝手に読むものでは無く、先生のもとで勉強するものです。
先生は、その文献の主題のみならず、サンスクリット語という言語はもちろん、
ダルマとモークシャについても、本人の生き方を通して教えられる人でなければなりません。
ダルマとモークシャについて、多くの人が、
正しい先生のもとで勉強を進められる社会でありますように。。
श्रीराम जय राम जय जय राम !
関連記事:
ラーマーヤナ日本語訳を冒頭から。。
ラーマとクリシュナ、対照的な誕生日の数字の謎
ラーマの誕生日、ラーマ・ナヴァミー
<< サンスクリット一日一語の目次へ
ラーマという名の王子の人生を描いた物語(アヤナ)
ですから、
ラーマ + アヤナ = ラーマーヤナ
となります。
母音の長短に気をつけましょう
長短を無視して、日本では「ラマヤナ」とか、
ラテン系だと「ラマヤ~ナ」など、いろいろ間違われているようですが、
正確には「ラーマーヤナ(रामायणम् [rāmāyaṇam])」です。
最初の2つの音節が長く、続く2つの音節は短く発音します。
ちなみに、最後の「ナ」 は舌を内側に反らして発音します。
詳しくは、下の「文法的な説明」 を参照してください。
サンスクリット語には、母音の長短の違いで
意味が全く変わってしまう単語が多々あります。
そしてなにより、口伝により継承されて来たサンスクリット語においては、
発音の正確さはとても重要ですから、
ひとつひとつの音を、マインドフルに発音しましょうね。
日本でよく見かけられる、母音の長短の間違いが起きている言葉は、
ヴェーダーンタ、サードゥ、プージャー、プラーナーヤーマ、等々でしょうか。
特に、短い i と u で終わる単語の最後が伸ばされているのと、
長い ā で終わる単語の最後が伸ばされていないのが気になります。
あと、日本語の小さい「ッ」のように、詰まるべき音が、
日本人の場合、詰まっていない、というのも気になります。
サティヤ、ニドラー、等々、このタイプはたくさん見かけます。
文字だけ追いかけていないで、きちんと耳から学んでくださいね。
ちなみに、1拍の長さの母音は、ह्रस्व [hrasva]と呼ばれ、
2拍の長さの母音は、दीर्घ [dīrgha]と呼ばれます。
発音する時は、長さの区別をしっかり意識して、
正しい発音を身につける努力をしてください。
ラーマーヤナという言葉の意味と語源
「ラーマ」とは、今でも存在するインド北部の都市アヨーディヤーの、
ダシャラタ王の息子である、王子の名前です。
「ラーマ(रामः [rāmaḥ])」の語源に関しては、
それだけでひとつの記事になるので、後日書きますね。
ヴィシュヌ神が、人間にダルマとは何かを体現して見せるために、
「ラーマ」という人間の姿をしてこの世に表れ、
その人生を描いた物語の文献「アヤナ」が、
「ラーマーヤナ」です。
”रामस्य चरितान्वितम् अयनं शास्त्रम् [rāmasya caritānvitam ayanaṃ śāstram]”
ラーマの行動に沿った文献
शब्दकल्पद्रुमःという梵梵辞典より
「アヤナ(अयनम् [ayanam])」は、
「行く」という意味の動詞の原形「अय् [ay]」を語源としています。
サンスクリット語の「行く」という言葉には、
様々な意味合いがあります。
単に、地点AからBへの移動、という意味もありますし、
その人の人格の表れである「行動」や、
そのような行動の連続である「人生・生き方」という意味、
そして「達成・成功」「ゴール」という意味もあります。
これらの意味が「アヤナ」という言葉に含まれます。
さらに、それらに沿って著わした「文献」という意味もあります。
文法的な説明
「ラーマーヤナ」という言葉は、サマーサ(複合語)というタイプの派生語です。
ヴィッグラハ・ヴァーキャ(派生語を説明する文章)は、
रामस्य अयनं रामायणम् ।
rāmasya ayanaṃ rāmāyaṇam |
となりますね。
サンスクリット語を学び始めたら、早い段階でサマーサを学ぶと良いですよ。
あと、अयन の न् が、ण् に変化するのは、राम の र् が原因です。
しかし、このルール(8.4.1, 8.4.2)が適用されるのは、
ひとつの単語内においてのみです。
サマーサの中の、前の単語(पूर्वपद [pūrvapada])にある原因が、
後ろの単語(उत्तरपद [uttarapada])にある न् を変化させることは出来ません。
しかし、8.4.3 पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः। というスートラにより、
固有名詞に限っては、サマーサの前後の単語にまたがった ण् への変化が認められています。
ラーマーヤナから学ぶべきこと「ダルマ」
ダルマの元型、ダルマとは何か、のアーキタイプ、
それがラーマです。
ダルマの体現である主人公ラーマが、
難しい状況をどのように乗り越えていくのかを、
物語から学び、ダルマを学びます。
この宇宙において、理性を与えられている生命体を人間と呼び、
その理性を正しく使って、その場その時の状況を判断し、
適切な行動を選びとり、実行できる人を、
ダルマに沿った人、つまり精神的に成長した人と呼びます。
思考ストップして、自分の頭を使わずに、
ただただ盲目的に宗教や国家の教義に従うのではないのです。
この宇宙の創造主は、契約書にサインすることを人間に課しているのではなく、
人間に理性を与えることにより、自分で理性的に考えることを課しているのです。
しかし、日々の生活の中で展開される状況は、
何が適切なのか、簡単に判断できないことが少なくありません。
ゆえに、ラーマーヤナやマハーバーラタなどの物語から学ぶのです。
これらの物語は、登場人物たちの判断の失敗から成り立っています。
ダルマが最重要視されるバックグラウンドにおいて、
様々な過去を持つキャラクターが、様々な難しい状況の中で、
それぞれに判断を下し、物語が進みます。
私たちに考えさせるための内容であり、
盲目的に何でも賛美して追従するための内容ではありません。
ヴェーダーンタはもちろんですが、このような歴史物語も、
ダルマとモークシャを知る先生から学ぶ必要があります。
ラーマーヤナについて
ラーマーヤナは、ヴァールミーキという名の著者によって、
サンスクリット語の韻文律に沿って描かれた歴史物語です。
それをもとに、インド各地の言語でご当地ヴァージョンのラーマーヤナが生まれました。
北インドでは、トゥラシーダーサのラーマーヤナが有名です。
ラーマーヤナという文献は、イティハーサという種類に分類されます。
イティ・ハ・アーサで、「ということでしたとさ」のような意味になることから、
歴史物語は、イティハーサという名前で呼ばれます。
https://valmikiramayan.net/
ソースとしては、こちらのサイトが充実していますが、
インドの文献は自分で勝手に読むものでは無く、先生のもとで勉強するものです。
先生は、その文献の主題のみならず、サンスクリット語という言語はもちろん、
ダルマとモークシャについても、本人の生き方を通して教えられる人でなければなりません。
ダルマとモークシャについて、多くの人が、
正しい先生のもとで勉強を進められる社会でありますように。。
श्रीराम जय राम जय जय राम !
関連記事:
ラーマーヤナ日本語訳を冒頭から。。
ラーマとクリシュナ、対照的な誕生日の数字の謎
ラーマの誕生日、ラーマ・ナヴァミー
<< サンスクリット一日一語の目次へ