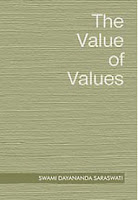セーヴァー(सेवा [sevā])
セーヴァーというサンスクリット語の言葉は、ヴェーダが教える伝統的価値観をよく表している言葉であり、恩師であるプージヤ・スワミジが、私達全ての人に話す時にいつも強調されていた言葉です。
私自身も、ヴェーダーンタに出会ってから毎日、私のすること、書くこと、話すこと、考えることの全てが、全てのものへのセーヴァーでありますように、と考えながら生きています。
ヴェーダーンタが教えるヴィジョンである、「自分と世界の本質について」に関わるトピックであるゆえに、以下とても長文になります。また、本来は直接話をするべきトピックなので、文面ではどうしても分かりにくくなると思います。きちんと理解したい人には世界中どこにでもお話に伺いますので、いつでもご連絡ください。
―――――――――――――――
消費者から貢献者への成長
―――――――――――――――
セーヴァーとは、与えられた状況の中で、貢献者として行動することです。
人間としての精神的な成長は、貢献者として行動することによってのみでしか得られません。
どのような状況においても平安で幸せであり続けていられるという、物理的だけでなく精神的に豊かな人生を送るためには、精神的な成長が必要とされます。さらに、人間として生まれて来た意味を完全に満たしてくれる自己の本質の知識を得るための準備が整えるためにも、精神的な成長は、最も必要とされる要因です。特にヴェーダーンタ(ウパニシャッド)で教えられている知識は、それを聴く人の精神的な成長が足りなければ、単なる小難しい哲学のような情報にしか聞こえず、自分のこととして理解されることはありません。
ゆえに、ヴェーダーンタを学ぶ人はもちろん、全ての人にとって、人生の出来るだけ早いうちから、セーヴァーという言葉が教える貢献者として行動する意味について知っておくことは、自分の人生を精神的に豊かな人生にする上で、とても重要なことです。
セーヴァーの姿勢とは、自分を取り巻く状況から、より利益を得ようとする消費者的な姿勢から、貢献者的な姿勢に変え、自分に出来ることは何かを考え、一歩踏み出して行動することです。
自分に出来ることは何かを考えるとき、基準となるのは、自分が相手の立場なら、と想像する、相手を思いやる気持ちです。
人間の心というものは、他の痛みを感じ取れるように出来ています。相手が人間であれ動植物であれ、相手の痛みを思い計り、痛みを取り除き、幸せを増やすのに役立つ行動を選びとることが、自分のすべきことであり、貢献者になるということです。
しかし、相手を思いやる気持ちは、自分の都合や好き嫌いといった条件によって阻害され、見えなくなってしまうことは往々にしてあります。ゆえに、状況を判断する目が、自分の都合や好き嫌いに染められていないか、意識する必要があります。これが、貢献者へと成長を飛べるための第一歩です。
自分がどのように行動すべきか分からない、という人は多いですが、それでも、他人がどのように行動すべきかについては、はっきり分かっているものです。
自分が他人にして欲しいことが、自分のすべきことであり、自分が他人にされたくないことは、自分がすべきでないことです。これくらいに当たり前に、全ての生き物に共通する法則を、サーマンニャ・ダルマ(普遍的秩序)と言います。
この普遍的な価値観を先天的に察することの出来る心を持っているのが、人間の心です。
人間なら誰でも、今ここで何をすべきかについて、だいたいのことは先天的に分かっている筈なのです。しかし、自分の好き嫌いによって心に曇りができて、都合よく、自分のするべきことが何なのかが分からなくなるのです。
普遍的な価値観に沿った行為を、ダルマに沿った行為と呼びます。人間の自由意志が、ダルマに沿った行為を選択する為に使われた場合、自由意志が人間らしく、賢明にうまく使われたことになります。
現代の社会では、より多くを消費することがより幸せなのだという概念が広く受け入れられていますが、ヴェーダの価値観では常に、貢献者へと成長を遂げることを推奨しています。なぜなら、消費者から貢献者へ変容することは、人間として本当の成長することであり、それは本当の豊かさをもたらすからです。
貢献者として世界に参加することを選ぶことによって得られる精神的な成長と精神的な豊かさは、ほんとうに生きていて良かったと思える人生を送るために必要であり、また、人生の本当の意味を完全に満たすためにも必要になります。ゆえに、自分が貢献者になることを選ぶこと、つまりセーヴァーの姿勢で世界に参加することは、ヴェーダの価値観のなかで強調されているのです。
―――――――――――――――
小さな自分という自己認識
―――――――――――――――
自分の本質を知らなければ、この身体この心でこの世界を認識している経験が絶対となります。ヴェーダーンタの教えによって、自分の本質は完全な存在であると聞かされても、自分の心が精神的な成長を遂げていなければ、ヴェーダーンタの教えはただの難しい哲学のようなお話にしか聞こえず、今ここにいる自分のこととして理解できません。
この広大な世界の中で、ほぼ見えないくらいに微小な点に過ぎないこの身体とこの心で自分を認識しているとき、自分という存在はあまりにも儚く無力な存在です。ゆえに、経験によって得られる満足感に完全に依存し、思い通りにいかなければ、当然の結果として、嘆き悲しむことになります。これが普通の人の自分と世界の認識です。
このような自己認識と世界の認識を持っているから、自分が世界と関わるときの態度が、消費者的な態度になってしまうのです。この世界の中で、とてつもなく小さな存在として自分を認識し、この世界から出来るだけ多くのお情けとおこぼれを頂戴して、安心を得て幸せになろうとし続け、それに終わりはありません。自分をこの身体この心で認識している以上、完全に満たされることが無いからです。
人間は誰でも、生まれたときは完全な消費者です。空気と食べ物を必要とし、また、周りの人からのお世話も必要としています。生き続けている間はずっと、このように世界からさまざまなものを受け取らなければなりませんから、消費者の側面を持って世界と関わり続けることは避けられません。
ヴェーダは、消費することを最小限に抑え、貢献を最大限にすることを、人間としての成長として教えています。それと正反対の価値観を教えるのが、現代の消費経済社会です。しかし、このような社会は、物理的にも経済的にも、そして倫理的にも当然の行き詰まりを迎えています。ゆえに、現代に生きる人々には、貢献者になろうとすることが人間としての精神的な成長と豊かさであると教えるヴェーダの人生観を、是非学んでいただきたいと願うばかりです。
人間は、生存本能が備わっているだけでなく、自分とは本質的にとても小さな存在だと認識し、それをどうにかしたいと根本的に切望しているので、放っておけば消費するばかりになってしまう傾向にあります。ゆえに、貢献者へと成長するためには、自由意思を使って、貢献者となることを選び取らなければなりません。人間に与えられている自由意志とは、この為にあるのです。そして人間の知性とは、自分は何をするべきかについて、正しく判断するために与えられているのです。
ヴェーダの価値観は、盲目的に従うだけの思考停止を導くものではなく、人間としての知性の力を最大限に使うことを推奨します。また、ヴェーダーンタの教える真実も、信じるものではなく、理解する為にあるのです。
ゆえに、ヴェーダでは、人間を人間たらしめている、人間の最大の財産である知性(メーダー、ブッディ)が、人間として生まれて手に入れられる幸福の追求に欠かせないものとして教えています。これが、ヴェーダという聖典が、他の宗教の聖典とは根本的に異なる点です。動植物は人間の消費の為だと神が仰ったのだから、盲目的に何も考えずに使い放題つかえばいいよ、というのではなく、神は人間に知性を与えたのだから、ちゃんと使ってね、ということです。
貢献者になることは良いことなのだと感じられる経験は、子供の頃から周りの大人が教えてあげることが出来ます。子供が何かを成し遂げたとき、たとえそれが小さなことでも、子供の目を見て、心から褒めながら、あなたのした事は私を幸せにしてくれた、あなたの存在は私の幸福に貢献してくれている、としっかり伝わるようにコミュニケーションをとれば、肯定的な自己認識と、貢献者になれるという自信を育てることに繋がります。
―――――――――――――――
大きな自分という自己認識
―――――――――――――――
多くの人は、「貢献しようにも、お金にも才能にも恵まれていない私なんて無理!」と言います。この「私なんて」という態度は特に日本文化に顕著かも知れません。セーヴァーを頼まれた場合、断る理由として、「私になんて無理です」というセリフがよく聞かれます。
たしかに、貢献者になるには、自分が状況よりも大きな存在でなければなりません。しかし、貢献者になるためには、有り余るほどのお金や才能は必要としません。自分の自己認識が、目の前の状況よりも大きければ、それで良いのです。
与えられた状況を客観的に見て、自分に何が出来るかを考え、それを行動に移すことが貢献するということです。今目の前にある状況が与えられているのと同様、自分が持っているものも全て、与えられています。自分の手足も時間も、自分を育ててくれた人々も、自分の頑張れる力も、全ては自分に持たされ、与えられ、目の前にある状況の一部を構成しています。この事実に気づいて、全ては自分が成長するために与えられているとして、状況を客観的に判断すれば、おのずと、この状況の中で自分がどのように貢献者として参加するのが適切なのかが見えてきます。
人間や動植物といった全ての生きるものの、痛みを減らし、幸福を増やすために、今目の前にある状況の中で自分が選択すべき行動はなにか?人間としての思考能力は、このようなことを考えるためにあります。
自分に出来ることを発見しているとき、自己認識における自分は、状況よりも大きな存在です。
―――――――――――――――
クル、セーヴァーム
―――――――――――――――
多くの人々が互いを思いやり合い、それを行動に移すことを全国的なレベルで可能にするために、プージヤ・スワミジは、セーヴァーという言葉を掲げた「AIM for Seva (All India Movement for SEVA、エイム・フォー・セーヴァー)」という活動を発足させました。僻地に住む子供たちが安全に通学できるよう、インド全国に100以上の寄宿舎が建てられ、スワミジのお弟子さんたちが運営や指導に関わっておられます。
また、幼稚園から大学までの文化的で質の高い教育機関や、医療機関も提供されています。
スワミジはヴェーダーンタのヴィジョンにもとづいた曲を多く作詞作曲されています。その中で、AIM for Sevaのテーマソングとして書かれた曲の繰り返しの部分では、「कुरु सेवां त्वं कुरु सेवाम्... (セーヴァーをしなさい)」というダイレクトなメッセージが私達に教えられています。
助けを必要としている状況に向かって、自ら歩み寄り、手を差し伸べる。
実際にどのような活動をされているのか、皆がどのような姿勢で行動しているのか、是非インドに行って見て来てください、そして、是非この活動に参加してみてください。
 |
| スワミジの生誕地にあるAIM for SEVAによる 幼稚園から大学までの教育機関の校庭にて。 毎朝の牛さん達のお散歩コース |
―――――――――――――――
グル・セーヴァー
―――――――――――――――
セーヴァーは、助けを必要としている状況に対して手を差し伸べるものだけではなく、グル・セーヴァーと呼ばれる、ヴェーダやヴェーダーンタを勉強するためのものもあります。教えを聴きたい、という動機によって行われることから、グル・セーヴァーは「シュッシュルーシャー(शुश्रूषा [śuśrūṣā]、聴きたいと望むこと)」とも呼ばれます。
ヴェーダーンタを学ぶ上で、セーヴァーが必要であることは、バガヴァッドギーター4章34節において、バガヴァーン自身によって、「完全なナマスカーラ、適切な質問、そしてセーヴァーをすることを通して、その(知識)を理解しなさい」と、「セーヴァー」という言葉を使って教えられています。
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।।4.34।।
ヴェーダーンタの教える自分の本質とは何かの知識を、単なる難しい哲学的情報でななく、自分自身の意味として理解することを望む人は、セーヴァーをする機会を積極的に見つけて活用するべきです。
ここで、私自身の経験の話をしますね。
私はコインバトールのグルクラムに移る前は、北インドにあるリシケシのダヤーナンダアシュラムにて、ヴェーダーンタとサンスクリット語文法、そしてチャンティングの勉強するための生活をしておりました。当時のリシケシのアシュラムでは、「コース」といったクラスはありませんから、勉強したいのなら、自ら先生のところに行って、「私のためにクラスをして下さい」と直々にお願いするところから始めなければなりません。
私が頼んだからといって、先生が必ずOKしてくれるとは限りません。先生には既にいろいろするべきことがあるでしょうし、また、私のために教える時間をわざわざ作る価値があるのか、と思うかもしれません。実際、クラスをして欲しいと頼んだのに、実際クラスを始めてみると、一回も来ない人やすぐに来なくなるという人は多く、先生の時間を無駄にさせてしまうことは多々あります。
このようなことから、まずは、私を教えるための時間を捻出してもらうために、先生を無駄に忙しくさせている作業を見つけ出して、肩代わりさせてもらえないかお願いするところから始めていました。それがきっかけで、クラスの準備として、教室を確保して掃除し、他の人を集めたり、書籍を手配したり、授業で使うサンスクリット語の書類を作ったり、校正作業をしたり、先生の代わりに簡単な英語やサンスクリット語を他の生徒に教えたりと、いろいろさせてもらうことが出来ました。クラス開催のための先生への直接のセーヴァーだけでなく、クラスを可能にしてくれているアシュラムのセーヴァーとして、オフィスや図書館、本屋、テンプルなどを手伝ったり、アシュラム内や近隣に住んでいるお年寄りのお手伝いや、アシュラムへの訪問者のさまざまな遣いっ走りなど、さまざまな活動をさせてもらうことが出来ました。
セーヴァーをしていく上では、指示待ちではなく、自分から、この状況でどうすることが、ダルマに沿っていて、人々の幸せを増やすことが出来るのか?を自分の頭で考えることが要求されます。このようなアプローチでの勉強環境の実現は、いろいろ大変だったかも知れないですが、より伝統的なアプローチであり、この勉強に対する必要なあるべき姿勢を体得させてもらう機会となったので、私はこのような環境で勉強を始められたことを、とても幸運に思っています。
プージヤ・スワミジは、セーヴァーという言葉の意味を、ヴェーダーンタのクラスを通して教えてくれただけでなく、スワミジの、思いやりそのものの生き方を通しても教えてくださいました。
その教えを受けて、実際に自分がリシケシのアシュラムで生活をしていて学んだことは、「他人がどうすべきか?」といったことは考えるだけ不毛なので、意識して一切考えないようにして、「自分が今ここで出来ることは何か?するべきことは何か?」だけを考えるようにすれば、生きていることが全く難しくなくなり、人生は充実したものでしかあり得ない、ということです。
自分が世界を見渡すとき、貢献者になろうとして自分と世界を見ていれば、難しいことや苛立たしいこと、不便さといったことはあっても、自分が不幸になることはあり得ません。「自分はこれだけ貢献しているのに、誰からも感謝されない」と嘆くのは、「相手は自分に感謝すべきだ」と、やはり「他人がどうすべきか」と考えている証拠です。
他人の言動に、自分の幸せを委ねているから、他人の言動を支配しようとしてしまうのです。自分が自分を肯定していないから、他人からの肯定的認証に心理的に依存するのです。
どれだけ多くのものに恵まれていても、本人が消費者目線で世界と関わっている限り、自分は不幸だと嘆くことになります。一方、たとえ傍目からは何も持っていないように見えても、自分が世界を見渡すときの姿勢が「ここで私が出来るセーヴァーは何か?」という貢献者的目線なら、「私は全てを与えられている」という事実に気づくことができます。
また私は、自分自身が先生方から受け取ったヴェーダーンタとサンスクリット語の知識を教え継ぐ活動もしていますが、その活動の全ても、セーヴァーの精神によってのみ成り立っています。私自身が、「教えないといけない」というプレッシャーを全く持っていないので、クラスの開催に関わる全ては、学びたいと真摯に願う人々によって、それだけでなくさらに、他の多くの人々にも学ぶ機会を提供しようとしてくれている、高尚な意思を持った人々によって運営されています。これは、ヴェーダを発見したリシ達から、ヴィヤーサ、シャンカラーチャーリヤ、そして私の先生まで綿々と続く、グル・パランパラー(知識伝承の系譜)にある先生方の恩恵の表れに他なりません。
このように、日本でクラスが出来るというのは、私にとっては奇跡的事象です。ですから、お客様的・消費者的態度で参加するのではなく、是非、貢献者的態度で、運営してくださっている方々に感謝し、手助け出来ることはないかと探す姿勢でクラスに参加し、学びの機会・成長の機会となるよう、希少なクラスを活用してください。
また、今年(2019年)の9月には、インドからパラマートマーナンダ・スワミジが日本の皆さんの為にヴェーダーンタを教えにいらしてくださいます。インドからスワミジをお呼びするということは大変なことで、多くの方面で多数のセーヴァーを必要としています。セーヴァーをする側として参加してみると、ただ聴いているよりも、はるかに多くのことを学びとることが出来ます。是非、勇気を持って一歩踏み出して、この機会を活用してみてください。
―――――――――――――――
ゴー・セーヴァー
―――――――――――――――
インドの伝統では、特に牛のお世話をすることを、「ゴー(牛)・セーヴァー」と呼び、今でもとても神聖な行為として、重要視されています。牛からとれるミルクや牛糞は、火の儀式やプージャーなどで捧げものとして使われるだけでなく、場を清めたり、薬品としてなど、インドの伝統文化の中で様々な用途で使われています。
ゴー・セーヴァーの精神では、ミルクを産出しない老いた牛や雄牛も、大切に飼育されます。直接的に何も生産していなくても、ただダラダラ生きているだけの牛達を、尊敬し、それなりのお金と人員を使って、大切にセーヴァーをするのです。動物を利用できるのが人間の特権ではなく、動物のセーヴァーを出来るのが、人間の特権なのだと、私達に教えてくれます。
これは、今の日本には、とても重要なことだと私は思っています。資本経済主義の社会において人々は、金銭的価値を生まないものは喰うべからず、という暴力的な価値観を振りかざし、自分自身を含めた社会を構成している全ての人々をジャッジし、結局、自分自身が苦しむ結果となっているように見えます。
自分は人間なのだから、人間的意思を使えば、他を生かすことが出来るし、自分は生き物だから、他によって生かされている。この当たり前の事実が、見えづらい社会になっているようです。このような、人間と自然との繋がりについて、インドの伝統的な価値観に沿った場所で牛のセーヴァーをしていると、いろいろ考えさせられます。ゴー・セーヴァーは、そのようなことを考えるためにもあるのではと思います。
―――――――――――――――
現代社会において見直されるべき、祈りという貢献
―――――――――――――――
最近、生きているだけで価値がある、というフレーズが聞かれるようになりました。動物の場合は生きているだけで貢献者になれるように出来ているので、本当に生きているだけでいいのですが、人間の場合は、意思を使って行動しなければ、なかなか貢献者になれなません。しかも人間は、貢献者として世界と関わっているという自覚を持って初めて、自分を受け入れらるという心理構造を持っているものです。
貢献者として世界に関わるということは、必ずしもより多くの金銭的価値を生んでいるということではありませんし、より多くの点数を取ったり、より高い役職についたりすることでもありません。それらは貢献になることもあれば、破壊につながることもあります。そして何よりも、貢献の仕方は人それぞれです。
生まれや育ちに関わらず、どんな人でも出来る貢献が、祈りです。どんな健康状態でも、経済状態でも、くよくよ悩むことが出来るマインド持っている人なら誰でも、マインドひとつで出来るのが、生きとし生けるもの全ての幸福を願う祈りです。祈りに必要なものは、たったひとつ、自分の自由意志だけです。マインドを使ってする行為も立派な行為です。自由意志を使ってされた行為は必ず結果を生みます。皆の幸せを祈ることによって、生まれや育ちに関わらず、いつでもどこでも誰でも平等に、社会貢献は出来るのです。
そしてその祈りを、言葉や行動へと表現していくのです。生きていることそのものが祈りになるのです。
祈りがどのように言葉やは、人それぞれ、その人の生まれや育ちや環境・状況など、様々なコンディションによって決定されますが、それは優劣の付けられるものではありません。皆それぞれ違った形で社会参加をしているから社会として機能しているのであって、そこに優劣をつけられるものではありません。どのような生まれでも育ちでも、それぞれに貢献の仕方がある。自分のするべきことをすることによって、どのような生まれでも育ちでも、精神的な成長を手に入れるチャンスは等しくある、というのがヴェーダのヴィジョンです。好きなことだけをするために、するべきことを放棄する。他人を蹴落として競争に勝つ。環境の循環機能を破壊して最大限に搾取する。
こういった、現代のいわゆる「成功像」は、人間の成長でも成功でもないということを、ヴェーダは始まりの無い時から知っていて、人間に教え続けてきたのです。それなのに、それがカースト制度だと歪曲されてしまったことは人類にとって不運なことです。
現代の自由競争社会では、自分のするべきことを放棄して好きなことだけをしたり、競争の中で他を蹴落として下剋上を達成したり、環境を破壊して搾取することが、人間の「自由の証し」として善しとされていますが、当然それでは無理があり、環境的・心理的にストレスが大きく、結局人間は本当に幸せになれないということを人間は早く学ぶべきです。
競争をしなくても、自分の居る場所で、自分に与えられたこの身体この心で、誰でも貢献者になれるのです。そのスタート地点は、生きとし生けるもの全ての幸せを祈ることです。それは立派な貢献です。「私は毎日生きるもの全ての幸せを祈ることを日課としている人間です」という自己認識に勝る自己肯定はありません。そして、この身体この心をうまく使えれば、その祈りを、人々に届く言葉や行動へと表現することも出来ます。それはその人それぞれで、その表現方法に優劣はありません。
―――――――――――――――
自分を知ること
―――――――――――――――
人間という生き物は、幸せの追求のためにある人生の中で、自分とは何者か?という自己意識が、最重要事項である生き物です。同時に、全ての人間は、自分という存在の本質を知らずに生まれて来て、さらに、それを知る由も体の中に持っていません。だから、自分の身体や自分の心、自分の持ち物など、自分を取り巻く環境で自分の価値を判断してしまうことは避けられません。
自分をジャッジする要因として、金銭価値や、その生産性といったものほど中身の無いものはありません。しかし現代の社会では、金銭価値という数字がそのまま人間の価値にとして受け入れられているかのようです。そのような基準で、自分と他をジャッジして、自分と他を窮地に追い込んでいるのだとしたら、それほど意味のない人生はありません。
また、自分の前世や来世、カルマなどで自分をジャッジしようと(もしくはされようと)する人々も多数います。しかし、それも小さな自己認識の上に成り立っています。この小さな自分が天国に行ったり生まれ変わったりしている以上、根本的な問題の解決に繋がっていないことには、何ら変わりはありません。
今後、ベーシックインカムの導入などで、生き延びるためにがむしゃらになって努力する必要がなくなり、目先の目標によって気を紛らわすことが出来なくなったら、人間はさらに、自分とは何かの問いに直面させられることになります。
この根本的な問いに完全に答えるだけでなく、毎日の生活の中での姿勢についてまでも含めた、トータルなヴィジョンを教えるヴェーダとヴェーダーンタは、今後人類がより注目すべき知識となるでしょう。
―――――――――――――――
終わりに
―――――――――――――――
ここまで長い文章を書きましたが、冒頭でもお伝えしたように、やはり、このような話は、直接顔を見ながら話し、聴くものです。文面だけでは伝わらないことが沢山あります。ですから、この文章を読んだだけで分かった気になるのではなく、きちんと理解するためには、是非、パラマートマーナンダスワミジのクラスはもちろん、私や私と同じ師を持つ先生方のクラスに出てみて、じっくり話を聴き、質問をしに来てください。
全ての人々の幸せを祈りながら。。
Medha Chaitanya