कृष्णः
[kṛṣṇaḥ]
masculine - クリシュナ

インド関係のことを少しでも知っている人なら
誰でも知っているだろう、ということで、
クリシュナ、といきなり固有名詞を訳にいれました。
孔雀の羽をつけて、
笛を持って、
いつも微笑んでいて、
青黒い肌をした、
牛飼いのハンサムボーイ、
という容姿が伝統で私達に与えられています。
このような容姿や形のことを、伝統的には「ウパーサナ・ムールティ」と呼びます。
私達の心は、色、形状、音などの「フォーム」とやりとりするように出来ています。
色や形が無い、抽象的で、形而上のアイディアであっても、
私達の経験や考えの全ては、最終的には、脳波の形です。
なぜ、ウパーサナ・ムールティが伝統の中で教えられているのでしょうか?
神様とは?全知全能とは?私達は何処から来た?
何のために生きている?死んだらどうなる?
この世の意味は?
といった人間として基本的な探求をする時に、
その人の心を、こういった容姿や形のものに持って行くと、
水先案内人のように、スムーズに答えに導いてくれますよ。
と伝統が教えているのです。
バガヴァッド・ギーターの冒頭の詩で、
रणनदी पाण्डवैः सोत्तीर्णा, कैवर्तकः केशवः ॥
’このマハーバーラタ戦争という、とても超え難い川を、
パーンダヴァ達は越す事が出来た。
なぜなら、ケーシャヴァ(クリシュナ)が水先案内人をしていたから。”
とあります。
クリシュナを味方につけるということは、
グレース(幸運)という、全ての成功に必要な要素の存在を認めて、
グレースを手に入れるために、ちゃんと手を打っている、と言う事です。
さらに、バガヴァッド・ギーターの中でクリシュナが教えを説きます。
先生を水先案内人として置く、ということは、
先生の教える智慧に、自分の思考とその基準を沿わせる、ということです。
道に迷ったら、出口を知っている人に道を聞くのと同じ事です。
クリシュナって誰?と聞くと、すぐに返ってくる答えが、
「ヴィシュヌ神の化身」「ヴィシュヌ・アヴァターラ」
ですが、それを聞いて何を分れと言うのでしょうか?
ヴィシュヌって誰?
神様に決まってるじゃん!
って、当たり前のように言ってるけど、
神様って誰よ?化身って一体何?
全知全能の本当の意味が理解出来たら、
見るもの全ては全知全能の神の表れです。
しかし、そんなことを言われても、
「スケールが大きすぎて、把握できない。。」
というのが、人間の頭脳です。
それゆえに、理解につながるための第一段階として、
人間の頭脳で把握できる、「形」が伝統の中で提唱されているのです。
それが、ヴィシュヌであり、クリシュナであり、シヴァであり、ドゥルガーであり、、、
と人間の好みの数だけ、神様の形も用意されているのです。
ではでは、本題のクリシュナの意味を見てみましょう。
कृष्णः [kṛṣṇaḥ] は、कृष् [kṛṣ] という動詞の原形から派生しています。
कृष् [kṛṣ] とは、「存在する」という意味です。
ण [ṇa] は、「幸福」を表しています。
伝統で語り継がれているクリシュナの容姿は、常に幸福を表しています。
笛を吹いたり、ダンスをしたり、周りの人達を皆幸せにしたり。。。
しかし、「存在する」を「幸福」とがどう繋がって、クリシュナになるのか?
आकृष् [ākṛṣ] という動詞の原形は「魅了する、心を引き付ける」という意味です。
人は誰でも、心が惹きつけられるものに幸せを見出します。
しかし、どんな幸せも長く続きません。
この宇宙の中にあるもの全ては、常に変わり続けているからです。
変化し続けているものは、それが「在る」といった瞬間に、既に変化しています。
私達の心も体も、物理的、心理的、様々なレベルで、変化し続けています。
そういったものを「絶対的な存在」と呼ぶ事は出来ません。
しかし、「じゃあ、無い」とも言えません。
私はここにいるし、つま先を机の角にぶつければ痛い。
つま先は在るし、机も在る。
姑に何か言われたらムカつく、ってことは、姑はいるし、ムカつく心も在る。
時間とともに生まれては無くなるものばかりだけど、ある、と言える。
その「在る」が、कृष् [kṛṣ] の意味である、「存在する」です。
そして、それが「幸福」のण [ṇa] なのです。
なぜ?
今までの人生の中で、来ては去っていった、沢山の幸せな時間を思い出してください。
私を幸せにしてくれた状況は、常に変化し続けている、宇宙の中の出来事でした。
その中で、常に、一定して在ったもの、、、
それは、「私」でした。
「存在」と「幸せ」のつながりが見えましたか?
そして、それが、私達が常に追いかけ続けているもの、心を惹きつけているものなのです。
これが、上で言われている「ウパーサナ・ムールティ」のことです。
<< 前回の言葉 33.クリパー(कृपा [kṛpā])<<
マハーバーラタの戦い、アルジュナの心理、
バガヴァッド・ギーターの背景などを説明します。

>> 次回の言葉 35.ケーシャヴァ(केशवः [keśavaḥ])>>
クリシュナの別名、ケーシャヴァについてサンスクリット語文法を交えて説明します。
[kṛṣṇaḥ]
masculine - クリシュナ

インド関係のことを少しでも知っている人なら
誰でも知っているだろう、ということで、
クリシュナ、といきなり固有名詞を訳にいれました。
孔雀の羽をつけて、
笛を持って、
いつも微笑んでいて、
青黒い肌をした、
牛飼いのハンサムボーイ、
という容姿が伝統で私達に与えられています。
このような容姿や形のことを、伝統的には「ウパーサナ・ムールティ」と呼びます。
私達の心は、色、形状、音などの「フォーム」とやりとりするように出来ています。
色や形が無い、抽象的で、形而上のアイディアであっても、
私達の経験や考えの全ては、最終的には、脳波の形です。
なぜ、ウパーサナ・ムールティが伝統の中で教えられているのでしょうか?
なぜ、このような容姿が伝統で教えられているのか?
神様とは?全知全能とは?私達は何処から来た?
何のために生きている?死んだらどうなる?
この世の意味は?
といった人間として基本的な探求をする時に、
その人の心を、こういった容姿や形のものに持って行くと、
水先案内人のように、スムーズに答えに導いてくれますよ。
と伝統が教えているのです。
バガヴァッド・ギーターの冒頭の詩で、
रणनदी पाण्डवैः सोत्तीर्णा, कैवर्तकः केशवः ॥
’このマハーバーラタ戦争という、とても超え難い川を、
パーンダヴァ達は越す事が出来た。
なぜなら、ケーシャヴァ(クリシュナ)が水先案内人をしていたから。”
とあります。
クリシュナを味方につけるということは、
グレース(幸運)という、全ての成功に必要な要素の存在を認めて、
グレースを手に入れるために、ちゃんと手を打っている、と言う事です。
さらに、バガヴァッド・ギーターの中でクリシュナが教えを説きます。
先生を水先案内人として置く、ということは、
先生の教える智慧に、自分の思考とその基準を沿わせる、ということです。
道に迷ったら、出口を知っている人に道を聞くのと同じ事です。
ヴィシュヌ神の化身(アヴァターラ)とは?
「ヴィシュヌ神の化身」「ヴィシュヌ・アヴァターラ」
ですが、それを聞いて何を分れと言うのでしょうか?
ヴィシュヌって誰?
神様に決まってるじゃん!
って、当たり前のように言ってるけど、
神様って誰よ?化身って一体何?
「神」の定義を試みてみましょう
宗教を持っている人も、持っていない人も、
「神様が、、」とか、「神様はいるの?」とか、「神様なんかいない!」とかも、
あたかも既に、神様が誰か知っているのが前提になっています。
それって、とっても変ですね。人間って面白いものです。
それって、とっても変ですね。人間って面白いものです。
信仰の厚い人でさえも、「神様って何???」ってちゃんと真面目に考えている人は、
この世に殆どいないように見受けられます。
一般的に定義されている、神様とは、、、
「信仰の対象」― 信じないと存在出来無い神様なんて、頼りになるのでしょうか?
「人知を超えた存在」― 要するに、解からない、知らないってことでしょ?
そんな掴みどころのない神様に、世界の人口の殆どが、
すがりついたり、人生を捧げたりしている事自体が、摩訶不思議に他なりません。
今までの手垢のついた「神」の曖昧な定義は横において、
今から、一からきちんと定義しなおしてみましょう。
まず大前提として、「神」とは、信じる対象ではなく、理解されるべき対象である。
ということです。
全世界の大多数は、「神」と言ったとたんに、知能がOFFになっています。
大事な事は、知能をONにして、ちゃんと正面に向かって、考えるべきです。
「全知全能」というのが、神様によくついてくる形容詞ですね。
全知 = 全部知ってる。
私が今何を考えているとか、どんな状況に置かれているとか、
いちいち報告しないと知らなかったり、報告しても気づいてくれなかったりするのは神様じゃない。
私の考えも、自然環境の在り方も、宇宙の動きも、全て、
脳神経学、生物学、物理学、素粒子物理学、、、などの知識の表れです。
その知識の全て = 全知
が、「全知」という言葉の本当の意味です。
これは、信じる必要性の全くない、理解出来ることです。
そして、理解されるべき事です。
全能 = 全ての能力
先ほど見た、「全ての知識」が、私の考えや体や、飼い猫や、お隣さんや、
政治情勢や、環境問題も含む、全ての「宇宙」として現れるために必要な能力のことです。
これも、信じるとか信じないとかいった議論ではないですね。
「全知全能」とは、理解し、認識するべき対象なのです。
全知全能の本当の意味が理解出来たら、
見るもの全ては全知全能の神の表れです。
しかし、そんなことを言われても、
「スケールが大きすぎて、把握できない。。」
というのが、人間の頭脳です。
それゆえに、理解につながるための第一段階として、
人間の頭脳で把握できる、「形」が伝統の中で提唱されているのです。
それが、ヴィシュヌであり、クリシュナであり、シヴァであり、ドゥルガーであり、、、
と人間の好みの数だけ、神様の形も用意されているのです。
「アヴァターラ」とは?
この前の、「ケーシャヴァ」の回で説明しています。
ヴィシュヌのアヴァターラとして良く知られているのがラーマとクリシュナ、
そして、仏教の開祖であるゴータマ・ブッダもヴィシュヌのアヴァターラとして数えられています。
そして、仏教の開祖であるゴータマ・ブッダもヴィシュヌのアヴァターラとして数えられています。
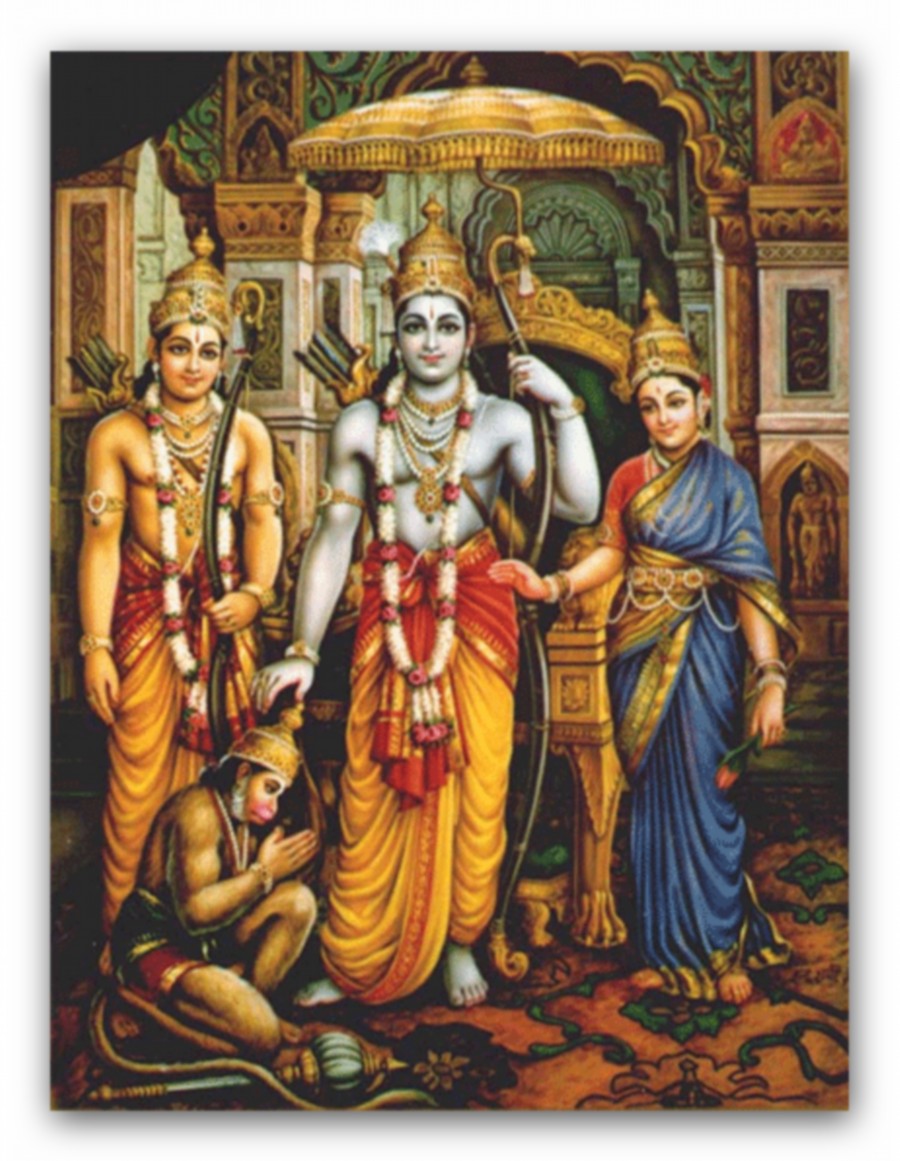 |
| コーダンダという名の彼しか扱えない大きな弓を持って、 直立しているのが、ラーマの姿勢。 ダルマ=正義を表している。 |
| いっぽう、クリシュナは笛を持って、 体をくねらせているのがいつものポーズ。 アーナンダ=幸せを表している。 |
ラーマが象徴するダルマ(正義、宇宙の秩序との調和)があって、
初めて、クリシュナの象徴するアーナンダが可能なのです。
ではでは、本題のクリシュナの意味を見てみましょう。
クリシュナの意味
1.永遠の幸福
कृष्णः [kṛṣṇaḥ] は、कृष् [kṛṣ] という動詞の原形から派生しています。
कृष् [kṛṣ] とは、「存在する」という意味です。
ण [ṇa] は、「幸福」を表しています。
伝統で語り継がれているクリシュナの容姿は、常に幸福を表しています。
笛を吹いたり、ダンスをしたり、周りの人達を皆幸せにしたり。。。
しかし、「存在する」を「幸福」とがどう繋がって、クリシュナになるのか?
आकृष् [ākṛṣ] という動詞の原形は「魅了する、心を引き付ける」という意味です。
人は誰でも、心が惹きつけられるものに幸せを見出します。
しかし、どんな幸せも長く続きません。
この宇宙の中にあるもの全ては、常に変わり続けているからです。
変化し続けているものは、それが「在る」といった瞬間に、既に変化しています。
私達の心も体も、物理的、心理的、様々なレベルで、変化し続けています。
そういったものを「絶対的な存在」と呼ぶ事は出来ません。
しかし、「じゃあ、無い」とも言えません。
私はここにいるし、つま先を机の角にぶつければ痛い。
つま先は在るし、机も在る。
姑に何か言われたらムカつく、ってことは、姑はいるし、ムカつく心も在る。
時間とともに生まれては無くなるものばかりだけど、ある、と言える。
その「在る」が、कृष् [kṛṣ] の意味である、「存在する」です。
そして、それが「幸福」のण [ṇa] なのです。
なぜ?
今までの人生の中で、来ては去っていった、沢山の幸せな時間を思い出してください。
私を幸せにしてくれた状況は、常に変化し続けている、宇宙の中の出来事でした。
その中で、常に、一定して在ったもの、、、
それは、「私」でした。
「存在」と「幸せ」のつながりが見えましたか?
そして、それが、私達が常に追いかけ続けているもの、心を惹きつけているものなのです。
2.青黒い色をした者
これが、上で言われている「ウパーサナ・ムールティ」のことです。
<< 前回の言葉 33.クリパー(कृपा [kṛpā])<<
マハーバーラタの戦い、アルジュナの心理、
バガヴァッド・ギーターの背景などを説明します。

>> 次回の言葉 35.ケーシャヴァ(केशवः [keśavaḥ])>>
クリシュナの別名、ケーシャヴァについてサンスクリット語文法を交えて説明します。

























