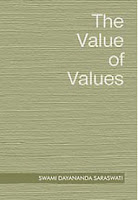アーユルヴェーダを学ぶ人にはおなじみの、ダンヴァンタリ様。
こちらのアシュラムに付属しているアーユルヴェーダの施設でも、
トリートメントを行うまえに、施す人と施される人が一緒に、
施術部屋にあるダンヴァンタリ様の神棚の前でお祈りをします。
お祈りとその意味は前にこちらで紹介しましたね。
ところで、ダンヴァンタリという名前はどういう意味なのでしょうか?
ヴェーダーンタとは直接関係ないので、そんなん知らんがな、なのですが、
最近何人かの人に聞かれたので、辞書を引いてみました。
शब्दकर्पद्रूमः というサンスクリットの百科事典を引いてみると、、、
धनुरुपलक्षणत्वात् शल्यादिचिकित्साशास्त्रं तस्य अन्तम् ऋच्छति इति । देववैद्यः, स भगवदवतारः ।
ダヌ(医学の知識の) + アンタ(終わりまで) + アリ(行く)
というデーヴァのお医者さん、ヴィシュヌのアヴァターラということです。
まず、ダヌ(弓、धनु [dhanu])とは、
シャッリャ(矢、शल्य [śalya])という名前の文献に代表される、
医学の知識の集合体を表しているそうです。
それの、アンタ(最後、結論、अन्त [anta])まで行く、もしくは得る。
つまり、 全ての医学の知識を有している者、となります。
次に、वाचस्पत्यम् という辞書を引いてみますと、
धनोः तन्निमित्तशल्यस्यान्तं पारमृच्छत।
ダヌ(弓、武器全般の代表)による痛みのアンタ(終わり、向こう側)に行く、
となっています。
プラーナという文献ですね。
ブランマヴァイヴァルタ、ヴィシュヌプラーナ、バーガヴァタなどに登場するそうです。
プラーナとは、
シュルティ(ヴェーダ)、スムリティ(マハー・バーラタ等)に続くプラマーナとされる文献で、
ヒンドゥーの神様をモチーフにしたお話の殆どは、プラーナで見つかります。
プラーナの中の数々のお話しの根底はヴェーダーンタであり、
シャンカラーチャーリヤは、自身のコメンタリーの中でヴィシュヌ・プラーナを
しばしば引用していますが、
なぜか、一番有名で大きいバーガヴァタからの引用はひとつもないということです。
インドには、プラーナの話を民衆に聴かせるのに特化した、
「ポウラーニカ」と呼ばれる学者がたくさんいます。
でも、ヴェーダーンタを勉強する人とは、かなり色が違います。。
ダンテラス(Dhanteras)という名前で、ディーパ―ヴァリ(ディワリ)の前の、
トラヨーダシー(満月から13日目)です。地域や宗派によって違いはあると思いますが。
2016年は、10月28日です。
<< 目次へ戻る <<
文法的にもうちょっと知りたい人は====
ダヌ + アンタ + アリ
ヌの最後の音「ウ(u)」は、後ろに母音(ここではア)が来ると、
Vの音に変化しますね。そう、ヤン・サンディです。
アリは、ऋ(行く) + इ(者、行動の主体)から成ります。
(उणादिसूत्रम्) ४.१४० अच इः ।
अन्त と अरि は、、、शकन्ध्वादिगण が आकृतिगण なのでそこで पररूपम् にしてしまう?
====================

ヨガとアーユルヴェーダと文法と、
ヴェーダーンタの関係
- パタンジャリへの祈りから読み解く
<< アーユルヴェーダのプレーヤー(祈りの句) <<
ダンヴァンタリへの祈りの句です。
こちらのアシュラムに付属しているアーユルヴェーダの施設でも、
トリートメントを行うまえに、施す人と施される人が一緒に、
施術部屋にあるダンヴァンタリ様の神棚の前でお祈りをします。
お祈りとその意味は前にこちらで紹介しましたね。
ところで、ダンヴァンタリという名前はどういう意味なのでしょうか?
ヴェーダーンタとは直接関係ないので、そんなん知らんがな、なのですが、
最近何人かの人に聞かれたので、辞書を引いてみました。
ダンヴァンタリの語源
शब्दकर्पद्रूमः というサンスクリットの百科事典を引いてみると、、、
धनुरुपलक्षणत्वात् शल्यादिचिकित्साशास्त्रं तस्य अन्तम् ऋच्छति इति । देववैद्यः, स भगवदवतारः ।
ダヌ(医学の知識の) + アンタ(終わりまで) + アリ(行く)
というデーヴァのお医者さん、ヴィシュヌのアヴァターラということです。
まず、ダヌ(弓、धनु [dhanu])とは、
シャッリャ(矢、शल्य [śalya])という名前の文献に代表される、
医学の知識の集合体を表しているそうです。
それの、アンタ(最後、結論、अन्त [anta])まで行く、もしくは得る。
つまり、 全ての医学の知識を有している者、となります。
次に、वाचस्पत्यम् という辞書を引いてみますと、
धनोः तन्निमित्तशल्यस्यान्तं पारमृच्छत।
ダヌ(弓、武器全般の代表)による痛みのアンタ(終わり、向こう側)に行く、
となっています。
ダンヴァンタリの登場する文献
プラーナという文献ですね。
ブランマヴァイヴァルタ、ヴィシュヌプラーナ、バーガヴァタなどに登場するそうです。
プラーナとは、
シュルティ(ヴェーダ)、スムリティ(マハー・バーラタ等)に続くプラマーナとされる文献で、
ヒンドゥーの神様をモチーフにしたお話の殆どは、プラーナで見つかります。
プラーナの中の数々のお話しの根底はヴェーダーンタであり、
シャンカラーチャーリヤは、自身のコメンタリーの中でヴィシュヌ・プラーナを
しばしば引用していますが、
なぜか、一番有名で大きいバーガヴァタからの引用はひとつもないということです。
インドには、プラーナの話を民衆に聴かせるのに特化した、
「ポウラーニカ」と呼ばれる学者がたくさんいます。
でも、ヴェーダーンタを勉強する人とは、かなり色が違います。。
ダンヴァンタリの誕生祭
ダンテラス(Dhanteras)という名前で、ディーパ―ヴァリ(ディワリ)の前の、
トラヨーダシー(満月から13日目)です。地域や宗派によって違いはあると思いますが。
2016年は、10月28日です。
<< 目次へ戻る <<
文法的にもうちょっと知りたい人は====
ダヌ + アンタ + アリ
ヌの最後の音「ウ(u)」は、後ろに母音(ここではア)が来ると、
Vの音に変化しますね。そう、ヤン・サンディです。
アリは、ऋ(行く) + इ(者、行動の主体)から成ります。
(उणादिसूत्रम्) ४.१४० अच इः ।
अन्त と अरि は、、、शकन्ध्वादिगण が आकृतिगण なのでそこで पररूपम् にしてしまう?
====================

ヨガとアーユルヴェーダと文法と、
ヴェーダーンタの関係
- パタンジャリへの祈りから読み解く

<< アーユルヴェーダのプレーヤー(祈りの句) <<
ダンヴァンタリへの祈りの句です。